甕(かめ)で仕込む世界最古のクヴェヴリワイン造りが、いま世界に広がっている。ここ日本でも2017年からクヴェヴリワイン造りを実践している造り手がいる。それが、北海道空知地方の「KONDOヴィンヤード」近藤良介だ。なぜ彼はクヴェヴリでワインを仕込もうと思ったのだろう。その理由と挑戦の道のりを追った。
夢にまで見たクヴェヴリ
 北海道に戻ったあとは、早速クヴェヴリを手配した。しかし、なぜかジョージアの職人に断られてしまう。手配するときに、職人に直接連絡せず、ワインの醸造機器の輸入業者を通じてクヴェヴリの発注をしたのが理由だった。近藤としては、正式な輸入手続きをとったほうがいいと業者を経由したつもりが、ワンクッションあったことで職人の気が変わってしまったのだ。ジョージアのクヴェヴリ職人の数は限られている。仕方なく、一旦ジョージアからのクヴェヴリ調達を諦めるほかなかった。
北海道に戻ったあとは、早速クヴェヴリを手配した。しかし、なぜかジョージアの職人に断られてしまう。手配するときに、職人に直接連絡せず、ワインの醸造機器の輸入業者を通じてクヴェヴリの発注をしたのが理由だった。近藤としては、正式な輸入手続きをとったほうがいいと業者を経由したつもりが、ワンクッションあったことで職人の気が変わってしまったのだ。ジョージアのクヴェヴリ職人の数は限られている。仕方なく、一旦ジョージアからのクヴェヴリ調達を諦めるほかなかった。
しかし、クヴェヴリによるワイン造り自体を諦めたわけではない。実は、パオロ・ヴォドピーヴェッツに会った後、すぐに北海道でクヴェヴリ造りを模索していた。相談していたのは、弟分とも同士ともいえる「さっぽろ藤野ワイナリー」の醸造家・浦本忠幸。近藤は、浦本がワイン造りを志した学生時代からさっぽろ藤野ワイナリーのアドバイザーを務めていた。自然とふたりには師弟のような関係性ができ、それぞれがワイン造りをするようになってからは、何でも情報交換しあう仲になっていた。
志向が似ていた二人は、甕でワインを造りたいということを同じ時期に感じていたという。まだ、近藤がジョージアに行く話が出る前だったため、ジョージア製のクヴェヴリは無理だろうから、どこか近くで造ってもらえないかと模索していた。
「土を使った焼き物なので、心ある人に造ってもらいたいと思っていました。浦本くんと話をしていてさっぽろ藤野ワイナリーの卸し先に教えてもらったのが、北海道の斜里町に大きな窯を構えていた斜里窯職人の中村二夫さんでした」
3人は知人を介して知り合い、2016年の年明けに初めて窯元を訪ねて行った。斜里窯の工房では、普段は器が造られているが、登り窯という大きな窯を使っている。古くは、水甕を造るのにも使われていたのが、この窯。クヴェヴリのような大きな甕も登り窯があれば造れるのでは、と中村にかけあってみた。すると、「おもしろそう」と乗り気で、製造を引き受けてくれた。
北海道産のクヴェヴリを造るに当たって、何か参考になるものがないかと調べると、北海道池田町の十勝ワイン「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」に国際交流で寄贈されたクヴェヴリの現物が展示されていることがわかる。早速、3人で現物を見に行き、構造をしっかりと脳裏に焼き付けた。そして、KONDOヴィンヤードとさっぽろ藤野ワイナリーの共同で斜里窯のクヴェヴリ製造にこぎつけた。
近藤は、扱いやすいよう樽と同じサイズの200ℓ程度を希望したが、登り窯の入り口の都合で、それより少し小ぶりの大きさで造られることになった。それでも、焼きあがった後、クヴェヴリが割れてしまいそうだったため、窯も少し広げたという。苦労もあったに違いないが、中村は「楽しい仕事をさせてもらいました」と振り返る。「普段は器を造っているので、なかなかできない経験でした。もう今、大きな甕の需要はないですからね」。かつて水道が発達する以前は、水甕で大きな甕を造る機会があったが、現在はない。職人として、ワインの容器という新しい道具造りにワクワクする気持ちがあったに違いない。
こうして、KONDOヴィンヤードの斜里製のクヴェヴリが6つ完成した。一緒に製作を依頼したさっぽろ藤野ワイナリーは、完成した斜里窯でひと足先に2016年ヴィンテージを発売している。
もう1つのクヴェヴリ
 余談だが、彼らが見学に行った施設は、1974年に設立された十勝ワインを紹介する観光拠点「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」だ。この建物は、古城のような見た目から町民に「ワイン城」と呼ばれ親しまれている。一説によると、ジョージアの首都トビリシ郊外にある山上レストランをモデルしたという。なぜ、十勝ワインにクヴェヴリが寄贈されたかについて、所長の安井美裕(よしひろ)に話を聞いたところ、意外なことがわかった。
余談だが、彼らが見学に行った施設は、1974年に設立された十勝ワインを紹介する観光拠点「池田町ブドウ・ブドウ酒研究所」だ。この建物は、古城のような見た目から町民に「ワイン城」と呼ばれ親しまれている。一説によると、ジョージアの首都トビリシ郊外にある山上レストランをモデルしたという。なぜ、十勝ワインにクヴェヴリが寄贈されたかについて、所長の安井美裕(よしひろ)に話を聞いたところ、意外なことがわかった。
1963年に全国の自治体で初となる酒類試験製造免許を取得してワイン醸造に取りかかった池田町では、技術研修とは別に町民をヨーロッパ諸国などに送るワインツアーを1972年から開始していた。現在まで20回程開催されているが、1984年の第7回の旅先が、グルジア時代のジョージア。参加者28人の町民にとって、とても印象深い旅になったようで、帰国後も「グルジア会」という交流会が開かれていたという。その有志で再びジョージアを訪れたところ、ジョージアの関係機関からその交流を記念し、クヴェヴリと横型の圧搾機が池田町に寄贈された。これが、近藤らが見たクヴェヴリだった。
その後、今から20年ほど前に当時の所長がクヴェヴリを参考に、池田町の「いきがい焼き」という素焼きの甕で、ワインを造ったそうだ。現所長の安井も、いきがい焼きの醸造を経験した一人。池田町産のケルナーでワインを皮ごと仕込み、ワイン城の地下(現・ワインセラー)にあった砂場に、いきがい焼きを埋めてワインを造ったのだという。いきがい焼きはそれほど大きくない甕だったため、わずかな量ではあったが、合計2回ほど販売された実績があった。
「ワイン造りでも何でも先取りするのが池田町なんですが、ちょっと早すぎましたかね(笑)。でも、こうしてジョージアワインが流行っているので、十勝ワインでもまたやれたらいいなと思っています」
おそらく日本初のアンバーワイン、ぜひとも復活してもらいたい。
天然素材・クヴェヴリ
 © 2012 by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia
© 2012 by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia
話を元に戻そう。同じ頃、近藤は岡崎にジョージアのクヴェヴリの注文がうまくいかなかったことを報告した。これを聞いた岡崎は、「生産者を通して掛け合ってみる」とトライしてくれた。これがラッキーだった。彼女が掛け合った生産者というのが、フェザンツ・ティアーズのジョン・ワーデマン。アメリカ出身ながらジョージアでクヴェヴリワインを造り、ジョージアワインを世界に広めた立役者だ。彼が職人にクヴェヴリを造ってほしいと直接依頼してくれたのだ。
ジョージアでもクヴェヴリ職人は数えるほど。しかも、製作時期は1年に1回、夏の時期に限られる。原料となる土を粘土にして棒状に積み上げていくのだが、名匠といわれるザリコ・ボジャゼ氏の場合、1日10cmずつしか作業しない。クヴェヴリは水分が土の中に残っていないようしっかりと乾かすことが肝心だからだ。その間は、いくつかのクヴェヴリが同時進行で造られている。
加えてクヴェヴリは、いまや世界中から注目される発酵容器。外国からの注文も多い。場合によって何年も待たなくてはいけない。それをフェザンツ・ティアーズのジョン・ワーデマンがなんとかしてくれたのだろう。近藤のクヴェヴリは、注文して翌年の仕込みに間に合うまでに完成。そして、フェザンツ・ティアーズによって壊れないように木の枠で固定して梱包され、岡崎の厚意によってワインの輸入コンテナに同梱して船で運ばれた。
紆余曲折を経てジョージアと斜里のクヴェヴリが空知に届いた。ジョージア製の750ℓと610ℓ、斜里製の90〜170ℓが6つ。ようやく夢にまで見たクヴェヴリが自分の元にやってきたのだった。
 © 2012 by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia
© 2012 by Ministry of Culture and Monument protection of Georgia
ここで改めて、クヴェヴリの構造と使い方について、おさらいしておこう。クヴェヴリはテラコッタと呼ばれる土でできた素焼きの甕。形は職人や地域によってやや異なるがおおむね卵型で、ヒョロッとしたものやぽってりとしたものとさまざま。大きさは、10ℓ程度のものから3000ℓくらいのものまである。ジョージアで使われているものは、1500〜2000ℓのものが多いようだ。大きさは設置するワイナリー(=マラニ)の広さやその銘柄に使うブドウの量を計算して注文される。
KONDOヴィンヤードの場合は、750ℓと610ℓがあるが、これは「人が入れる最低の大きさ」とオーダーしたらこの容量のものが送られてきた。人が入れるサイズを依頼したのは、直接入って掃除をしたほうが清潔にできるからだ。
クヴェヴリは2つがセットになっていて、大きい方が収穫後に潰したブドウを入れて発酵期間が終わるまで入れておくもの、小さい方がそれを移し替えて熟成期間に入れておくもの。大きさが違うのは発酵時に液面が上がるのを考慮されているからだ。
クヴェヴリには粘土状になる土が原料として使用される。ジョージアでは職人が山で土を選びながら手作業で掘られる。選んだ粘土はこねられて手頃な棒状に成形され、1本1本をすり鉢状に積み上げていく。このとき型などは使わず、頼るのは手の感覚のみ。成形が終わると乾燥を待って窯で焼成する。大きなクヴェヴリを焼くにはそれ相当の大きさの窯が必要になるため、それも成形と同時に造られることが多い。
その後、内部に蜜蝋を塗り込んで液体の滲出やバクテリアの侵入を防ぐ。さらに外側にもセメントを塗ってコーティングを施す。大きな甕になると、成形もさることながら焼成温度や時間、蜜蝋をまんべんなく塗り込む作業はかなりの経験や勘を必要とする。その職人は数える程しかいない。
この工程でもわかるとおり、クヴェヴリはすべて天然素材で造られている。甕に使う粘土は石灰を含んだキメが荒いものが使われているので液体が呼吸しやすい一方、内部から蜜蝋を塗りこむことでバクテリアの発生を防ぎ、外側のセメントにも殺菌作用がある。使い終わったら、きれいに洗えば何百年も持つという。ワインにとっても、それを飲む私たちにとっても、地球にとっても優れた発酵容器なのだ。
北海道仕様のマラニ造り
 クヴェヴリが手に入ったら、次はクヴェヴリ用のワイナリーであるマラニ造りだ。KONDOヴィンヤードは近藤良介・智子夫妻と弟の近藤拓身、同じく岩見沢市栗沢町でワイン造りをするナカザワヴィンヤードの中澤一行・由紀子夫妻の3世帯5人で共同出資する「栗澤ワインズ農事組合法人」を設立し、2017年のワイナリー建設と自社での醸造スタートを目指していた。もちろんKONDOヴィンヤードはここへクヴェヴリを埋めてマラニを造る。ワイナリーは、地下に3つの世帯それぞれの地下ワイン貯蔵庫、1Fに共同して使用する醸造器具が置かれる。クヴェヴリは1F部分の地面を掘り下げる形で埋めることが計画されていた。
クヴェヴリが手に入ったら、次はクヴェヴリ用のワイナリーであるマラニ造りだ。KONDOヴィンヤードは近藤良介・智子夫妻と弟の近藤拓身、同じく岩見沢市栗沢町でワイン造りをするナカザワヴィンヤードの中澤一行・由紀子夫妻の3世帯5人で共同出資する「栗澤ワインズ農事組合法人」を設立し、2017年のワイナリー建設と自社での醸造スタートを目指していた。もちろんKONDOヴィンヤードはここへクヴェヴリを埋めてマラニを造る。ワイナリーは、地下に3つの世帯それぞれの地下ワイン貯蔵庫、1Fに共同して使用する醸造器具が置かれる。クヴェヴリは1F部分の地面を掘り下げる形で埋めることが計画されていた。
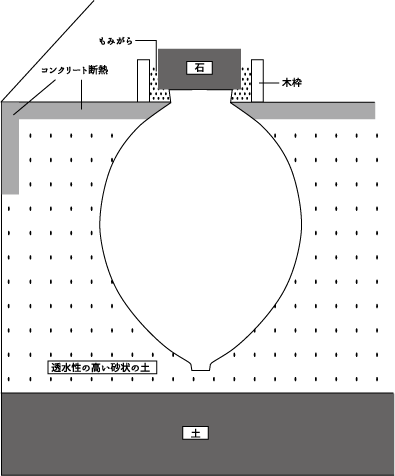
 通常、ジョージアのような気候エリアであれば、建物の1F部分の地面にクヴェヴリを埋めて、基数分を並べればいい。土の中ならば冬も夏も一定の温度に保てるからだ。ジョージアでは屋外にマラニを造っているところさえある。しかし、北海道は寒冷地。池田町のワイン城のように、地下室をさらに掘り下げれば気密性も高く温度を一定にすることができるが、KONDOヴィンヤードのマラニは木造の1F部分にあり、冷たいすき間風が入るため、低温対策が必要だ。
通常、ジョージアのような気候エリアであれば、建物の1F部分の地面にクヴェヴリを埋めて、基数分を並べればいい。土の中ならば冬も夏も一定の温度に保てるからだ。ジョージアでは屋外にマラニを造っているところさえある。しかし、北海道は寒冷地。池田町のワイン城のように、地下室をさらに掘り下げれば気密性も高く温度を一定にすることができるが、KONDOヴィンヤードのマラニは木造の1F部分にあり、冷たいすき間風が入るため、低温対策が必要だ。
北海道・岩見沢の冬は寒い。冬のある日、外気が−10℃だったときに室内の気温を測ると−6℃だったというから、地表近くにある液面はそのままだと凍ってしまうことになる。さらに土の中では「凍上」が起きる可能性がある。凍上とは、地下の水分が凍って地面が持ち上げられる現象。クヴェヴリが割れてしまう恐れがあるのだ。そのため岩見沢の凍結深度である60cmまでコンクリートを打って側面を断熱した。冷気は上からもやってくるため、上部のコンクリート断熱も必要だ。
 クヴェヴリの周りは、ジョージア同様に地震などでクヴェヴリが割れることがないように、周りを石灰を混ぜたセメントで補強した。クヴェヴリを埋める土には、水分が出て凍らないよう透水性の高い砂を混ぜた土を採用し、絶対に凍らないように配慮した。さらに発酵後に蓋を閉じた後は、蓋の周りに木枠を置き、もみがらでも断熱補強をした。クヴェヴリは、一度埋めてしまったら動かすことができないし、土の凍上や地震に対しても建設時に注意しなければならない。ジョージアではクヴェヴリを埋める場所を決めるのに、牛が腰を下ろした場所で決めるという習わしがある。家の中でも神聖な場所として扱われてきた歴史があるのだ。マラニは現代の醸造家にとっても、畑をつくるときのような慎重さが必要なのかもしれない。
クヴェヴリの周りは、ジョージア同様に地震などでクヴェヴリが割れることがないように、周りを石灰を混ぜたセメントで補強した。クヴェヴリを埋める土には、水分が出て凍らないよう透水性の高い砂を混ぜた土を採用し、絶対に凍らないように配慮した。さらに発酵後に蓋を閉じた後は、蓋の周りに木枠を置き、もみがらでも断熱補強をした。クヴェヴリは、一度埋めてしまったら動かすことができないし、土の凍上や地震に対しても建設時に注意しなければならない。ジョージアではクヴェヴリを埋める場所を決めるのに、牛が腰を下ろした場所で決めるという習わしがある。家の中でも神聖な場所として扱われてきた歴史があるのだ。マラニは現代の醸造家にとっても、畑をつくるときのような慎重さが必要なのかもしれない。
お話を聞いたのは・・・
近藤良介
KONDOヴィンヤード代表
北海道空知地方でワインを醸造。
2007年に初めて畑を拓き、2020年で14年目。
ソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールを
「タプ・コプ」「モセウシ」として瓶詰めする一方、
さまざまな品種の混植を「konkon」で瓶詰め。
2017年のブドウからkonkonをクヴェヴリで醸造。
2020年春にリリースを予定している。
<発売情報はHPにて確認できます>
http://www10.plala.or.jp/kondo-vineyard/
<KONDOヴィンヤードのワインが飲める店>
くりやまアンド・アム(北海道栗山町)
取材協力:岡崎玲子(ノンナアンドシディ)、浦本忠幸(さっぽろ藤野ワイナリー)、中村二夫(斜里窯)、安井美裕(池田町ブドウ・ブドウ酒研究所)、ジョン・ワーデマン(フェザンツ・ティアーズ)以上、敬称略・登場順
写真提供(一部):KONDOヴィンヤード、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所、ジョージア政府観光局、ジョージア文化・遺跡保護省











コメント